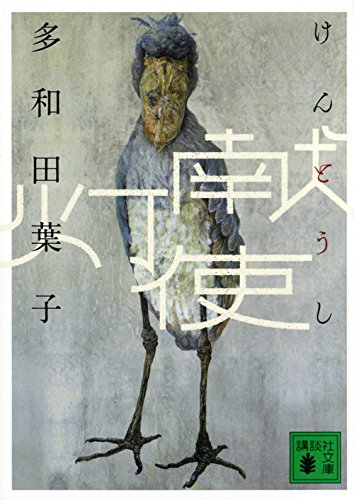「現実は、小説よりも…」
令和2年2月
「献灯使」多和田葉子(ページ数は講談社文庫第6刷版))
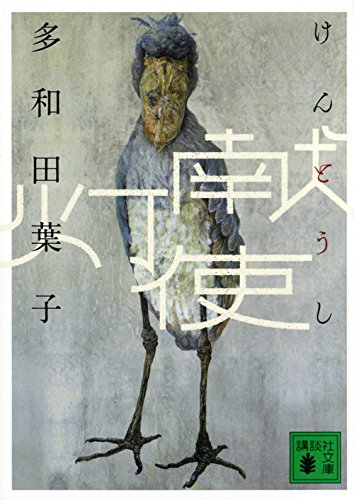
作中に放射能のことが書かれており、原発事故のことがイメージされているようだが、「あざとい」「書かれ方が軽すぎ」といった批判があった。
無名が15歳になるのを境にダークトーンな文章になっている。暗い世相になったのを描こうとしているのでは?との指摘あり。
9歳の時の砂の上でのじゃれあいが明るい希望になっている。
色が何かを象徴している。
たとえば、「青」は緑のことを「あお」ということがあり、素晴らしいのどかな平和なイメージをもたらす色とされる。
「レモンは目の前が青くなるほど酸っぱいね」P56などと表現される。
言葉遊び、言葉の持つイメージをストーリーに活かそうとする工夫もあったようだが、どうだったろうか。
「ジョギング」のことを「駆け落ち」というようになったP9、などは、現代の言葉でももともとの意味から離れて使われているものもあるからわからなくはない。
(NHKのびじゅチューン的な感じで空想を膨らませれば?)
しかし、「沖縄の言葉を売り飛ばす」P112とは、具体的にはどういうふうなことがなされたのかが書かれていないのでピンと来ない。
本作は、原発事故後をイメージしたディストピア小説と言われているらしい。
しかし、この読書会が開かれているころに「新型肺炎・コロナ肺炎」が流行し、
この病原体がどうやら人為的に作成されたものであるしく(つまりウイルス・生物兵器)、
これを作り出した人々の意図の邪悪さとか、
事故なのか故意なのか分からないけどその経緯の不可解さ、
なんとなく自由に議論することもはばかれる雰囲気など、
この得体の知れなさが支配する漠然とした恐ろしさときたら…
この現実のほうが、本作より格段にディストピア感がまさっている。
皮肉なめぐり合わせである。
トップページに戻る