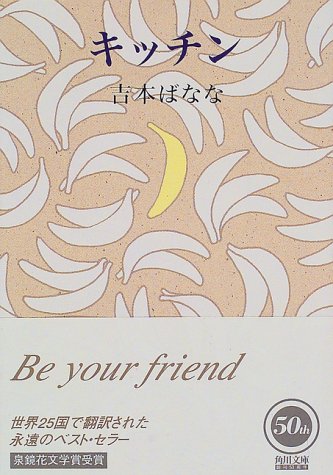「世の中に、この私に近い血の者はいないし、どこへ行ってなにをするのも可能だなんてとても豪快だった。」P16
令和2年1月
「キッチン」吉本ばなな(ページ数は角川文庫第50刷版))
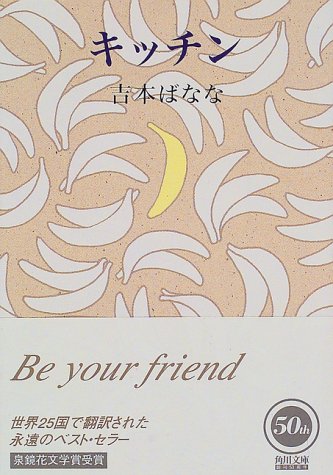
文章自体は読みやすいけど、女の子がだらだら話しているように書かれているので鼻についたという人がいた。
読み易さや、物語の簡素さの中にも、読み終えてみると何か引っかかるようなものが心に残る。
それは、例えば、「先日、なんと祖母が死んでしまった。びっくりした。」(7ページ)とか、
「思わず、おじいさんの古時計を口ずさんでしまいながら、私は冷蔵庫をみがいていた。」(34ページ)などのように、
よく考えると変な振舞いが随所に出てきているからである。
おばあさんが死んだら、普通そのとき生じる感情は「悲しい」ということになっている。
しかし読者のうちのいくらかは、自分たちのおばあさんが実際に死んだとしたら、
恐らく「びっくり」するという方が当たっている感情を抱くのだろうなあ、と想像するのではないだろうか。
あるいは、少なくとも「びっくり」するという感情はよく分かる、という人か。
ところが、ステレオタイプな「死」の表現は、悲しみによって描かれる。
そのことに読者は慣れている。作者はそのズレを巧みについているのだ。
言葉というのは、インフレを起こす。
例えば、悲しみを表現するのに、「とても悲しい」という言葉を使う。
しかし、この「とても悲しい」という表現が乱発されると、「とても悲しい」という言葉によってイメージされる感情は、慣れによって次第に弱いものになる。
そこで、「めちゃくちゃ悲しい」「死ぬほど悲しい」など、形容詞を強めることでそれを補おうとする。
しかし、結局表現の陳腐化によって、イメージされる感情は弱まってしまう、という連鎖が、言葉のインフレである。
日常生活で、ちょっと疲れただけで「すごく疲れた」などと言ってしまうのと同じだ。
言葉のインフレで、言葉がインパクトを失いうのを避けるために、吉本ばななは、ずれた表現を使ういるのである。
ずれた表現を用いることで、言葉は読者に迫力をもって立ちあがってくる。
また、爽やかな読後感の理由として、性的な描写がない、ということが挙げられる。若い男女が一緒に暮らす、という場面が、セックス抜きで描かれている。
親の目が光っているという物理的制約も、道徳や因習といった精神的制約があるわけでもないのに、である。
これはとても爽やかではあるが、現代ふうではない。これも、読者に違和感を生じさせいる原因である。
そして、セックス抜きで、濃厚な恋愛小説を書くために、作者は、キッチンを出してきている。セックスによって男女が結ばれるということをゴールにするのではなく、
食卓を囲むという日常の風景を一緒に作っていける相手が結ばれるべき異性なのだ、ということだ。
キス→ペッティング→セックス、という直線的儀式を飛び越えて、この人が自分の家族としてずっと目の前にいるとしたら、自分は幸せだろうか、という考え方をすることは、
セックスやの「愛」やのが、それこそインフレによって価値をなくしている現代では、私達の胸を強く打つ。
こうして見ると、みかげも雄一もえり子も、一見ずれているようで、実はとても合理的な考え方をしていることが分かる。
しかし、周りに理解はされにくい。
だから、みかげは恋人だった宗太郎とうまく行かなかったし、雄一は付き合っている奥野さんと摩擦を起こし、
えり子はストーカーに殺される。
みかげが雄一にカツ丼を渡しに行くときに苦労したことに暗示されるように、多数の人間と違うというだけで、彼らには多くの困難が待ちうけているのである。
物質的には豊かで、バブル時代の幸せ感が漂っている。
冒頭では、台所で寝るということに違和感がありすぎて、主人公は擬人化されたネコかなにかかと思ってしばらく読みすすめてしまった、という人がいました。
トップページに戻る