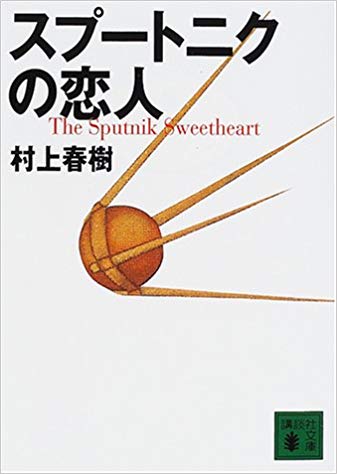「どこかで犬の喉を切らねばならないP250」
令和元年12月
「スプートニクの恋人」村上春樹(講談社文庫、ページ数は第35刷版)
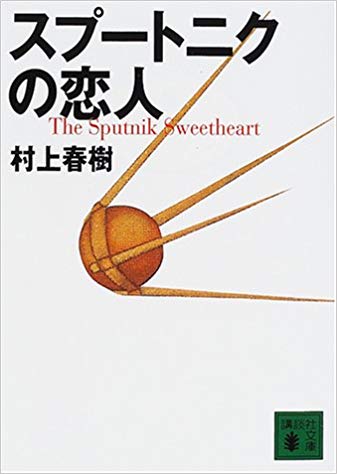
作家志望の大学生・すみれが、ひょんなことから個人貿易商「ミュウ」の助手として雇われ、一緒に海外出張にいったところギリシャのロードス島で行方不明になってしまうという話。
すみれは、小説家になりたいが文章を書き散らすばかりでなかなかモノにならない。その理由を主人公(「僕」)は、古い中国の城壁を作るときの逸話を出しながら助言する。「城壁には古戦場で死んだ兵隊の古い骨を塗り込め、そして生きた犬を屠ってその血を吸わせることで呪術的な力を得る」P26。主人公はすみれが小説家になるためには大きく欠けているものがあると喝破する。
ミュウもまた、すみれには良い小説を書く資質があるが、いまはその準備ができていない。だから「今は私といなさい」P58と半ば強引に自分の個人事務所にくるように説得する。(そしてすみれもミュウに恋をしていた)
つまり、主人公もミュウも、すみれが小説家になるためには決定的な何かが欠けていることに気づいていた。
古い中国の城壁に、古い骨と生きた血が必要であるように、すみれにも生々しい何かが必要なのだと。
特に、ミュウはピアニストになるために自分の全てを供物として捧げた(P75)にも関わらず、優れたピアニストになれないことが分かった。そして断念した。そして「本当の私の半分になってしまった」P73という。
ミュウは失った人間であるからこそ、すみれが欠けていることに気がついたのである。そして、ミュウはすみれに必要なものを与えることができる人間でもあった。
こうして見ると、主人公とミュウは、すみれが小説家になるための犠牲者、古い骨・屠られた犬というふうに見ることができよう。
しかし、すみれはなぜ行方がわからなくなったのか?どこにいったのか?
会ではいろんな意見が出ました。
・電話がかかってきたのだから、近いうち日本のどこかで会えるのでは。
・いや、電話がかかってきたというエピソードは主人公の願望が幻覚になって電話の音が聞こえたということだと読んだ。
・立派な小説家になって、海外で急に名前が取り上げられるとか。
・やっぱりこの世にはもういない、ということかな。島のどこかで死んでいる…
などなど。はっきりとした結論は出ず…
ほかに、
・フェルディナンド、ミュウの父、すみれの父はハンサムで威圧的な容貌。父に抑圧されてきたのであろうか。島では男の銅像があるが、忘れられて鳥のフンにまみれている。島では抑圧から解放されていたのかもしれない
・電話はいつも途切れそうで、さながら人工衛星からの通信のようである
・「スプートニクの恋人」とは、スプートニクの、が恋人にかかると見做すこともできるし、スプートニクであると同時に恋人である、という同格として取ることもできる
などの指摘がありました。
P270より。
「人にはそれぞれ、あるとくべつな年代にしか手にすることのできないとくべつなものごとがある。それはささやかな炎のようなものだ。注意深く幸運な人はそれを大事に保ち、大きく育て、松明としてかざして生きていくことができる。でもひとたび失われてしまえば、その炎はもう永遠に取り戻せない。」
それにしても、何と無自覚に失われていくことの多い世の中であることか!
トップページに戻る