「r>gの時代の終焉に生きるやんごとなき人々を描いた絵巻物」
平成30年8月
「細雪」谷崎潤一郎(ページ数は新潮文庫上第120刷、中102刷、下103刷版)
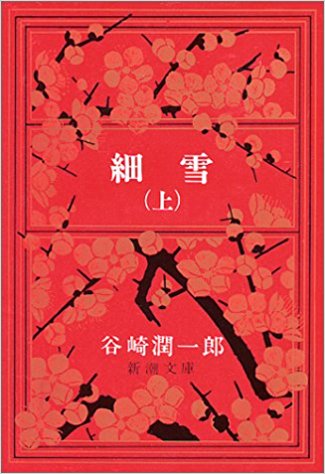
私は、この小説を20代の時にも読んだことがある。
その時は、ひたすら雪子がお見合いして、周囲の好意(おもには雪子にお似合いの相手を見繕ってお見合いをセッティングすること) をどんどん無下にする雪子に、苛立たしさ腹立たしさを感じた。
嫌なんだったらはっきり嫌、と断らないことにやきもきしたものだった。
しかし、今回読んでみて、雪子は決して無礼な人ではない、雪子のやり方で人に対しているのだ、というふうに思った。
作中では、雪子は寡黙で、あまり自身の意見を明確に述べることはしない人物として描かれている。
そんな雪子にお似合いの男性を探してあげよう、と周りがきりきり舞いをするわけなのだが、
選んできた男性は周囲の者(おもには上の二人の姉)がお似合いだと思っているだけで、当の雪子はそれほど良いとは思わない。
そもそも、お見合いをセッティングしてほしい、などと進んでお願いしているわけではない。
言ってしまえば、周りが勝手に騒いでいるだけなのだ。
しかも、雪子が本当に気に入るタイプをまったく理解していない。
家の格といったことに拘泥して、周りの都合を押し付けているだけなのだ。
今回読んでみて、お見合いがなかなかうまくいかないのは、雪子がわがままで優柔不断だからではなく、周囲の無理解のためなのだ、と思い至った。
フランスのリラダン伯は、「生活?そんなものは召使にまかせておけ」と言ったそうだが、
雪子はまさに生活を召使に任せて、生活臭さから切り離された浮世離れした本物の箱入り娘なのだろう。
本物の貴族は、自分から動くことをしない。
自分で考えたり意見を述べたりすることすらしない。
そんなことをするのは、はしたない、と思っている。
召使どもがすべて誂えてくれるのを待つだけなのだ。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
フランスの経済学者ピケティが、資本主義社会の格差が広がっていく理由について、
「資本収益率rは経済成長率gを上回る(r>g)からである」と巷間でもてはやされる理論について、数百年単位で各国のデータを独自に調べ上げて実証してみせた本がとても流行した。
すなわち、すでにある資本から生み出される利子のほうが、給与所得の伸び率よりも大きいから格差は拡大していくのだ、とピケティは主張する。
日本では、戦後、大規模資本は解体され、現代に生きる私たちは、豊かになるためにはいかに高給与を獲得するか、という発想になっているが、
本作の時代は、(いかに高給与であろうとも)給与所得で生活を算段するなんて、資本を持っている貴族からみたら「はしたない」ように見える時代であったのだろう。
上の二人の姉も読者のほとんども、おそらく「召使」なのだろう。
戦争の黒い影がすぐそこまで近づいてきているのに、呑気で生活感がない子爵家の庶子・御牧を雪子が選んだのは、私は前回読んだときは滑稽に見えたが、今回読んでみて何とも言えない哀切を感じた。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
参加者からは、雪子はいやいやお見合いをしているのか、どうなのか分からない、登場人物それぞれに嫌な点があって読みづらかった、
洪水のところだけやけに丁寧、亡命貴族など外国人のことも書かれているので、作者はもっと外国のこともストーリーに乗せていきたかったのでは?
書かれた原稿は4,5倍のページ数があったが、それを推敲していまの形に落ち着いたらしい、
などの意見がでました。
末の妹の妙子が腹痛になって入院し死にかけるところの描写はリアルで、若い女性が性交時に感染して腹腔内に細菌がはびこるフィッツ・ヒュー・カーティス症候群としてみれば矛盾がなく真に迫っている。
肝臓に炎症が波及することがある、と医師が警戒しているところなど。
谷崎潤一郎は、今でいうADHDや人格障害と言われるであろう人をリアルで丁寧に描いている。普遍なもののエッセンスをうまくすくい出す才能が、人々を魅了するのだろう。
↓おまけ、今回のホワイトボード…
トップページに戻る