「真に邪悪なものは、繊維の奥に潜んでいるかもしれない」
平成30年2月
アルベール・カミュ「ペスト」(ページ数は、新潮文庫第70刷版)
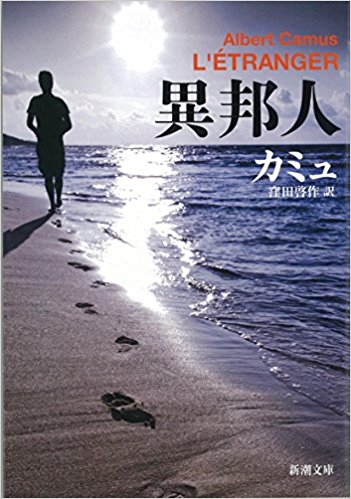
ひとつの街に「ペスト」という災禍がもたらされた時、人々はどのようにそれに対処するのか?
多くの者は、恐怖とストレスのため思考停止に陥り、危機が眼前に迫っていることから目をそらし危機の存在を認めようとしなくなってしまう。病気の専門家であるはずの医師たちの中にもそういう者が多いと作中では描かれる。
しかし、中にはこの危機に早くから気づき、そのリスクを適切に判断し、周囲に警鐘を鳴らして危機に立ち向かうことができる者が少数ながら存在する。主人公リウーのように。
リウーの誠実さや街の危機に対して真摯な対応を見て、はじめは戸惑うばかりだった人々の中にもリウーに感作され危機に立ち向かう勇気と行動力を持てるようになる者が徐々に現れてくる。それにより、街は多くの犠牲を払いながらも次第に回復していく。
人体に病原菌など異物が侵入すると、免疫反応が惹起される(獲得免疫)。T細胞が異物を適正に判断し、その構造情報を感知してB細胞に抗体を産生するように指示をする。B細胞はT細胞からの刺激で、異物に対する抗体を産生し異物を無害化・除去する。
ちょうどこの作中人物たちの動きをなぞらえているかのようである。
この作品が書かれた頃には、ワクチンや血清は経験則的にその効果が知られていたようだが、免疫細胞が複雑な役割分担をしていることなどはまだまだ未知のことであったはずだ。ひとつの生物個体の中で起こっていることが社会全体の動きと似ている、自己相似。フラクタル。
現代では、ペストに対する標準的治療は抗生物質投与であるが、作中の時代はまだまだワクチンや血清に頼るしかなかったようだ。(作中では、ワクチンと血清を混同していると思われる節がある。それが当時の最新の治療で作者も取材不足であったのだろう。また、命を救うだけの血清を何十人分あるいはそれ以上を作るとしたら、人手と相当の量の動物などの材料と時間がかかるはずなのだが、カステル医師はどうやって血清を作ったのだろうか…?)現代でもペストは恐ろしい病気のひとつではあるが、治療法が限られていた当時は現代の何倍もの恐怖感があったことであろう。
参加者のひとりは、SIRS(全身炎症反応症候群)がアジアを発生源に世界的に流行した時にアメリカを旅行し、ニューヨークの雑踏をマスクをして咳き込みながら歩いたらどんどん人が避けてくれてとても歩きやすかったという…
本作では、ペストは不意に出現して社会に対して破壊的なダメージを与えるものとして描かれているが、作者は本作のペストをナチズムになぞらえているとしばしば指摘される。
現代でも、「ペスト」と相似形をなす状況は起こりつつないだろうか?それにいち早く気づいて警鐘を鳴らす者はいるだろうか?そういう者を無視したり否定したり馬鹿にしたりしてはいないだろうか?
ペストは部屋の隅や穴蔵や着物の繊維の奥に常に潜んでいる、と作者は最後に警告している。
トップページに戻る