「discommunication…」
平成29年6月
「プレーンソング」保坂和志(ページ数は中公文庫第14刷版)
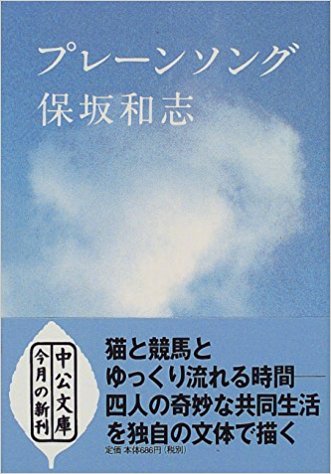
参加者の多くが、文章は読みやすいけど、ページを読み進めていくのがしんどかった、と感じたようです。
全体的な印象としては、一つの文章が長くて読みづらい、まどろっこしい、何も起きないということでタイトル通り平坦な感じで耳当たりの良い口笛をずっと聞いているような感じ、などの感想が出ました。
作者は本作で「ストーリーを作らずに小説は書けるのか?」という挑戦をしていると思った、との感想もあり。
ストーリーが平坦な割に読み進められるのは、ひとつひとつの場面描写が上手だから。たとえばp158のよう子が汗をぬぐう場面は、ふだんからこういうことをよく観察しているからこそ書けるんだろうなと思った、という意見もあり。
総じて登場人物に野心や欲望が感じられない。少女まんがの登場人物のように脱臭された感じがする。
暇な人間の、暇な時間を描いているだけだからつまらない。実は全員幽霊だった、というオチかもしれないと思った。
のんびりしていて、ストーリーを展開させる駆動力を感じさせないのは、登場人物たちを拘束する規律というものがないからであろうか。
子宮の中で遊んでいる胎児のように、ゆみ子が言うところの「母性的空間」に遊んでいるのかもしれない。
解説でも指摘されている、まず表情を提示してから、それを見た受け手の感情を描写する、という細かい時間の順に出来事を描いているのは、特段読みにくい感じはしなかったが、小説が進んでくるにつれて、その書き方にこだわらなくなっているように思われた、作者も面倒くさくなったのかな?などの意見がありました。
また、あまり働かなくても楽観的でいられるのはバブル期の若者の特徴だろう、というのは参加者全員の一致した意見でした。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
作家は何かほかの人に伝えたいことがあって作品を書くはずである。では、本作で作者は読者に何を伝えたかったのであろうか?
何も起こらない、何気ない日常を描き出すこと、というのは作者の狙いの一つであったろう。
会では、その「何も起こらないことを小説にする」ことの難しさについても話が出た。
森鴎外はじめ、多くの作家が何気ない日常を小説に描き出そうと試みてきた。その作品を書く動機は、きっと、自分が生きた、リアルに知っている時代の雰囲気や考え方や人々の心持ち、その時代の空気そのものを残しておきたかったからではないだろうか。1980年代の好景気の中で生きる楽観的な若者像を真空レトルトパックにするつもりで。
まるで、何気ない風景写真を誰かが後世の人々のために撮って残しておいてくれているように。なるべく、無味無臭な言葉で。
そう、そしてこの無味無臭な言葉、というのもなかなかのくせ者だ。
言葉というものは、複雑な人間の感情を極端に省略した符丁に過ぎない。だから、ある人がある言葉を聞いて想像するものは、ほかの人が同じ言葉を聞いてまるっきり違うものを想像してしまうかもしれない、という危惧を常に孕んでいる。
例えば、「楽しい」という言葉を聞いて、万人がまったく同じ感情を思い浮かべるとは限らない。むしろ結構、人によって違っているのではないだろうかと思う。
あるいは、私たちは「シャクトリムシは、鳥などの天敵から身を守るために木の枝に見せかける擬態をしている」などという言い方をすることがある。
これはよく考えてみるとおかしな表現だ。
おそらく、シャクトリムシは、鳥から見て自分が木の枝に見えているから助かっている、という自覚はないであろう。ただ、天敵が近くにいることを認識したら、木の枝に捕まって直線になって動かない、という本能に組み込まれた装置によって行動しているに過ぎない。
私たちは、分かっていながら、敢えてこのような本来とは異なるふうに情緒を交えた説明をすることがある。
これらは、無意識のうちに、なかば不可抗力的に、言葉に感情を表現するための機能を過度に背負わせている例であろう。無意識なのでやむを得ないと言えるかもしれない。
しかし、私たちは確信犯的に、言葉が意味するところが各人ごとにずれがあることを分かっていて、それを積極的に利用することも多いのではないか。
あるいは、そういうズルをする人々を容認したり。
コミュ障などという言葉が流行る昨今であるが、言葉による本当の相互理解が、どの程度実践されているのか、はなはだ心もとないものである。
↓おまけ、今回のホワイトボード、登場人物一覧…
トップページに戻る