「年年歳歳 花美しく、歳歳年年 人同じからず」
平成28年12月
「山の音」川端康成(ページ数は新潮文庫第101刷版)
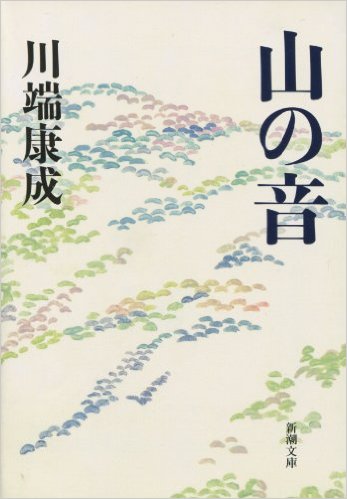
大きな事件が起こらず、淡々と物語が進んでいく。終戦から数年経った、都心から若干離れた鎌倉の家で起こる人間模様が描かれている。
司会からは次のような質問を考え、Q1,2,3,5,6を会で投げかけました。
Q1、本作を映像化するとしたら、信吾、修一、菊子、房子は誰が演じる?
Q2、ずばり、菊子は何歳か?
Q3、菊子が堕胎した理由は?信吾と修一はどう考えているか?
Q4、堕胎のあとで修一と菊子の関係が修復した理由。
Q5、ずばり、保子は義兄と関係を持ったか?
Q6、菊子は、今後どうなっていくか?修一との関係と、仕事を持つか?
Q7、菊子は、ヨソの人か?ウチの人か?房子は?
Q8、「自由」とは?P367,375。
この小説はそもそもどういう物語と読むか、ということについて、「信吾と菊子の恋愛小説」とか「信吾の老いの話」と言った意見が聞かれました。
信吾の恋愛小説、というのは広い意味ではそう取れるかもしれないけれども、作中では信吾は性的な能力はもはや衰えていることが何度か仄めかされている。
家のリーダーが高齢で力が衰え、日本の社会も強い男親が牽引する時代から男女同権で夫婦を家庭の中核とするのが基本と制度変更され、男性性が失われたことの苦悩や矛盾が描き出されているように読める。
菊子は、古い日本の象徴ともいえる信吾に(過剰なまでに?)敬愛の情を見せるが、それと同時に知的で進取の気風に富む進歩的な女性としても描かれている。堕胎を選んだのも、愛人を囲っている修一への抗議としての行いで、男女同権意識が強いためとも考えられる。
それに対して、房子は周囲の状況に流されがちで依存的なくせに他責的であり、いわば古い時代の女性のひとつのタイプと言えるかもしれない。(「房」の字は乳房を連想させ多産で豊かなイメージだ、と記号的な読み方ができる旨の指摘もありました。)
出戻りの房子は、信吾が菊子ばかりを可愛がっていると被害妄想的に(とばかりもいえないが)苦情を述べ、「実の娘を疎んじている」と詰る。
信吾は、いったんよその家に嫁いだ房子を「ヨソの人」とみなし、息子の配偶者を「ヨメに来た」とウチの人間というふうに考えるところが無意識にせよあったのではないだろうか。
ほかに、
・いろんな種類の花が出てくるのは、何かの象徴だろうか。蓮の花は何度も出てくるのは、永遠の生命の象徴だと思われるが、老いで体力が衰えた信吾には特に思い入れが強いのだろう。
・絹子さんと池田さんは、女性同士で関係を持っている、というのが仄めかされていると指摘あり。ついでに、谷崎英子も同性愛仲間ではないか、こんなに修一と絹子を別れさせようとするのはおかしい、その言い方も変だ、との指摘あり。
司会はまったく頓着していなかったので、指摘にビックリ驚きました。
…などの話も出ました。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
敗戦という大きな価値観の転換が行われた日本が舞台だけに、今に生きる私たちが読んでもよく分からない面があるようだ。(トマソン化?)海外でも評価が高いとのことだが、敗戦後の日本の雰囲気など、本当のところをどの程度分かって読まれているのだろうか?疑問に思うが、むしろこういう小説を読んでこのころの日本の制度や社会の雰囲気を理解していたのだろうか…
例えば、「家」「家長制度」。戦前は親子関係が重視され、家が社会の末端細胞として重要視されていたし、生産・消費・家族構成員の再生産(つまり生殖)の場として社会経済的に機能していたが、戦後は専制主義的であるとして廃止された。そして新憲法の下で、夫婦関係を基本とする新たな家族制度が発足させられることになった。
信吾の家も、信吾と修一は同じ会社で働いているようだが、家庭から切り離された場所であるし、消費活動にしても、家族で行動するよりも、事務員を誘ってダンスホールなどに行くことが多いようだ。
さらには、生殖の機能。菊子は妊娠したにもかかわらず、堕胎をしてしまう。修一はそんな菊子を冷ややかに見ている。しかも同時期に修一は浮気相手に子供を孕ませる。そして菊子は潔癖だから自分を許さないのだ、とも理解している。
家が存在意義を失って、家族というシステムが機能しなくなりつつある状況を描いたように見える。
↓おまけ、登場人物の関係図…
トップページに戻る