「雨ニモマケズ、の精神で」
平成28年8月
「恥辱」J.M.クッツェー
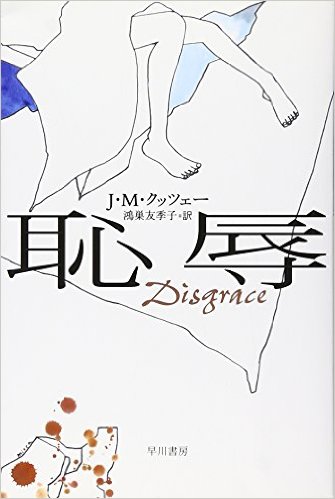
「恥辱」(ページ数はハヤカワepi文庫第2刷版)
ストーリーは平易で読みやすいが示唆に富んでおり、適切な省略がなされているので内容は大変濃い。登場人物たちの心情や主義は複雑で細かく計算されている。慎重に手がかりを拾いながら読み進めないと読み誤ってしまう作品である。
Q1、タイトルでもある「恥辱」とは誰にとっての何であるか?
Q2、作中特に査問会のところでデヴィッドは「有罪を認める」と何度も出てくるが、「有罪」とはどんな罪であるとデヴィッドは考えているのか?
Q3、登場人物の誰が白人で、誰が黒人(原住民)であるか?特にメラニー、ぺトラスは?
Q4、どうしてルーシーは自分の農地にこだわっているのか?
Q5、作中では暗示や象徴が多用されている。可能な限り指摘してみよ。
Q6、同じく作中では、ダジャレや一つの言葉が複数の意味を持っているのを利用して言葉遊びをしている。可能な限り指摘してみよ。
これらのポイントを丁寧に押さえていくことで、作者が意図するところが浮き上がってくる。
そして、これらのほとんどは作中にきちんと明示されている。先入観に流されてはいけない。
A1、ルーシーがレイプされたのにデビッドは黙っていなければならないこと。169P
ただし周りの人間はデビッドが大学を追われ農園暮しをしているのを恥辱とみている。266,267P
A2、恋に真剣に(serious)なれない、愛を巧みに扱いすぎること。絶頂の時間でさえ熱くならない。また、その結果メラニーを困らせてしまったこと。265P、299P
A3、写真参照。メラニー・アイザックス一家はおそらく黒人である。3人の強盗とペトラスも黒人。
A4、作中ではほとんど語られないが、例えば「農園を去ったら負けになるから」など。248P
A5、デヴィッド→犬(「年老いて」「陰嚢が大きい」「音楽を理解する」「殺される」存在だから、デヴィッドは犬に共感を覚えた)、デヴィッド→羊、老人→イギリス(斜陽である)、カーネーションの色→肌の色(白と赤を混ぜる、白人と黒人の交わり)、女性→土地、などなど。
A6、(翻訳にてヒントが示されている。)
デヴィッドは、大学の職を追われたことは、ほとんど後悔していない。彼が後悔しているのはメラニーを傷つけ失ったことである。
また、作中でも触れられているが、大学で教授と学生の恋愛が「虐待」と言われるようになったのはつい最近のことである。
ある時代には露見したらちょっとからかわれる程度のことだったのが、ハラスメントなどと言われるようになり、さらに虐待になった。
そんなに悪いことなら、可能な限り調査するべきなのに…などと思ってしまう。
ただし、デヴィッドとメラニーについては、事情を知らない者から見たら、良い点数で単位をあげるから私と寝なさいと強要した、という可能性があるように見えることは注意しなければならない。これは、査問委員会にて、メラニーから話を聞いて、強要したわけではないことは委員会のメンバーは分かっていたことであろう。しかし、悪意を持って伝える学生新聞などの手前もあり、デヴィッドからも強要した事実はないことを言ってもらいたいのだが、彼は頑なに弁明を拒否する。
これはなぜか?
デヴィッドは、「恋愛を裁く」ということがナンセンスであるということを態度をもって示したかったからではないだろうか。
仮にもワーズワースやバイロンを専門とする文学部教授として。
弁明拒否を貫いた結果、大学を辞めさせられることについて、デヴィッドはまったく後悔していない様子だ。
デヴィッドにとっての恥辱は、ルーシーの農園に行ってから体験される。
すなわち、「娘のルーシーが3人の黒人の強盗に家を荒らされレイプされても、訴えることができない」という状況に追いやられる。
デヴィッドはルーシーに、農園を離れるように説得するが、ルーシーから疎まれた挙句、「その場にいなかった」217Pくせになどと言われてしまう。
「その場にいなかった」とは複層的な意味を持っている。
デヴィッドはレイプが行われていたとき、同じ家にいたかもしれないが、気絶して別の部屋にいたにすぎない、という意味。
または、レイプされる苦痛が分からない、というやや抽象的な意味。
「女になる力は父にはない」247P。共感力が欠如している、とルーシーは元文学部教授の父親に向かって強烈に批判する。
レイプはきついものである。しかし、ルーシーは黙って耐えた。(叫んでいたら殺されていたろう、と作中でも述べられている。)
さながら、農園に居着くための通過儀礼のように。
その結果、子供を孕んだ。祝福されざる子供だろうか?
もし、憎むべき相手から苦しみを加重されたと考えるならば、祝福されざる子供であろう。
ところがルーシーはそう考えていないようだ。
確かにレイプされての妊娠は手痛い。しかし、子供はその土地の実力者で庇護者になり得るペトラスの保護を受けるカードになる。
そもそも、何千年何万年という人類の代を継いできた歴史の中には、原始の時代などでは無理やり性交させられることなどずいぶんあったはずであろう。
強力な統治機構と法によって保護されてきた時代のほうがずっと短い。大英帝国が斜陽になって、植民地に取り残された白人は、現地の法に従わなければならないのである。
人間はこうやって交雑していくのだ、とルーシーは悟っているように感じた。宮沢賢治の「雨ニモマケズ」のように。
ルーシーは、自然に親和性があるキャラクターのようだ。デヴィッドはルーシーを見て「先祖返りを起こしたような」などと言っているが、デヴィッド自身も農園生活に入ってみると、哀れな犬のために泣いて涙が止まらなかったり、空腹の羊のために怒ってあげたりするなど、自然と共鳴するキャラクターのようだ。実はよく似た親子なのだろう。
巧みに肌の色の記述を避けている点のも注意すべきである。メラニーなど。
ページがかなり進んでからメラニーは親が現地人っぽい人間ということで白人ではないことが仄めかされている。
そこで読者は足元をすくわれたような気持ちになる。白人のカッコ良い教授とラブロマンスを演じる相手は、無意識のうちに白人である、と思い込んでいたことに。
読者の内奥に潜む差別意識に。
小説の読者は、自分から離れた舞台で役者たちが演じる演劇をみているようなもので、自分とは切り離されたものだと思っているが、決してそうではないとこを思い出させる。
お前はただの通りすがりではない。立派な利害関係者だぞ、と見ず知らずのこの髭面の外国作家は不敵な笑みを浮かべて、何食わぬ顔をして通り過ぎようとした私に警告する。
油断ならない作品である。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
この小説で作者が伝えたかったことのひとつは、人間がその土地に根付く、ということについてであろう。
先に工業的発展を遂げたという有利な立場を利用してアフリカやオセアニアなどに植民地を作って回ったイギリス。
これらの土地に行った白人には、皮膚がんが多発する。日光の強さに皮膚が適応できていないからである。
(逆に黒人がヨーロッパに長く住むと、くる病にかかりやすい。褐色の皮膚が日光を遮りビタミンDの合成を阻害するからである。)
テクノロジーの発達、国際世論の変化によって優越的立場を失った宗主国民は植民地に取り残され孤立し、むしろ迫害される立場となる。
そんな人々がしみじみその土地に根付くのはいつのことか?
合意を得て、あるいは不当に、あるいは不本意ながら、血が混じり合いながら代を経て、その土地の光に肌が馴染むまでどれほどの時間がかかるだろうか?
↓おまけ、登場人物の関係図…
トップページに戻る