「名前とは、なんだろうか?」
平成27年12月
「壁」安部公房
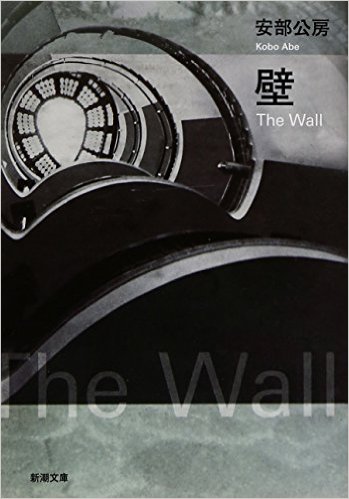
「壁」安部公房(ページ数は新潮文庫第96刷改定版)
名前とは、なんだろうか?
たとえば、「柴犬」という言葉。犬、と言わずに柴犬、と言うということは、柴犬をほかの犬とは区別するためにそのように名付けた訳である。
人の名前も、本来は誰かと区別して意識に上らせるために用いられる符牒に過ぎないもののはずである。
しかし、特定のモノに対して反復してその呼称が使われているうちに、名前のほうが別な意味を持つようになる。「名を成す」「名を汚す」「名前負け」などの成語が示すように。
ほとんどの人間が、普段の自分の名前に寄りかかっている部分も大きいのではないだろうか。
この小説は、名前が文字通り独り歩きして、自分から遊離してしまったとしたら?という、いわば思考実験をしようとしているのである。ただ、実験の前提が壮大すぎて、かなり抽象的で判然としない部分もあるきらいもある。
名前を「迂闊にも」失った人は、裁かれるべき存在になってしまうのか?名前を使って名前に頼って生きる人はカルマを背負っているとまで言われなければならないのだろうか?
私は、名前が無いという人に会ったことがある。
小さいころに親に捨てられ、偶然通りがかった人にずっと家の中で育てられ続け、ひょんなことから家を出て行き倒れてしまったという人だ。だから、正確な年齢も分からない。話しているだけなら、普通の若者と特段変わった印象はなく、暗い影を背負っているとは感じられなかった。
私は、その人のことを時々思い出す。その人からは世界はどんな風景に見えていたのか?心配や不安はどんなふうに感じていたのか?
親に捨てられ社会から存在を認知されていない、というと大変不幸なようにも思えるが、意外とさして不自由なく生きていけるものらしい。むしろ、何のしがらみも無いということは豪快なことなのかもしれない。
名前が無いことは不幸だ、という先入観を持ってしまうことは、それこそ「壁」が指摘する名前に寄りかかった価値観なのかもしれない。
本作は、安部公房が持っていたイメージのコラージュのように、その後彼が発表する作品のモチーフが詰め込まれている、物が生命を持って動きだしたり、裁判もどきで言葉遊びをするトートロジーはルイスキャロルの「アリス」に似ている、といった指摘も出ました。
今回も充実した議論ができました。
参加者の皆様に感謝申し上げます。
予告編のページ
トップページに戻る