「誰のために何を祈るのか?」
平成27年3月
小野正嗣「九年前の祈り」(ページ数は、文藝春秋誌2015年3月号版)
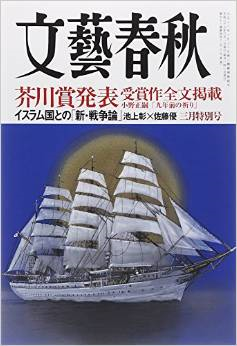
主人公のさなえは、カナダ人との間に生まれたおそらく自閉症圏と思われる子供を抱えて右往左往するシングルマザーである。 状況的に行き詰まり、母の勧めもあって実家に戻るのだが、さなえは田舎にありがちな詮索好きで迷信を信じがちな母に辟易している。 たとえば、犬を飼っていると、気持ちが犬のほうに向いてしまうので子供ができにくくなる、などと言う。
さなえはそんな母親を毛嫌いしつつも頼っている。
母親も、さなえが無理のある恋愛に嵌っているのを動物的直観で察知して、地元に就職先まで用意して実家に呼び戻したりする。
また、希敏がパニックに陥らないようにする対処法をテレビで研究したりもする。
つまり、母親はさなえに若干過干渉ではあるものの、愛情を持って接しているようだ。
対して、さなえはどうだろうか?
希敏について、医師からの診断と対応方法について、自分が受け止めきれないからという理由で、ほかの家族に伝えない。
ショッピングモールでそっと希敏から離れ、希敏がパニックを起こした時の周囲の反応をなかば興味本位で眺めている。
希敏は急な予定の変更や普段の生活と異なるなど、変化を嫌うはずなのに、自分の都合で文島行きを決めて気軽に変更している。
こうしてみると、さなえは思考が浅くて他責的なところがある人物として描かれているようだ。
つまり、精神的に幼いさなえが、その幼さゆえに苦境に立ち、困難に適切に対処できずおろおろしている、という状況なのだ。
そこに、実家に戻ってみたら、さっそく、みっちゃん姉こと「渡辺みつ」の消息を知らされる。 みっちゃん姉は、9年前に町主催の旅行でたまたま同道しただけという関係性だが、 ホテルの部屋が同室になり彼女の身の上を聞いて同情を寄せた相手だと思い出す。 (9年前なのでかなり曖昧な記憶だが。)
みっちゃん姉の兄とその息子は、ゴミ処理業者として生計を立てていて、そのゴミのために顔面にやけどの跡みたいものができ、
みっちゃん姉の息子も精神発達に異常をきたした、という不思議なエピソードを語る。
病が癒えるという文島の貝殻と、ゴミは対照的に描かれている。
そんな業が深いことを嘆いているかのようなみっちゃん姉が、たまたま入った海外の教会で一心不乱に祈っている。
ここでみっちゃん姉が何を祈っていたのかは、本当のところは不明で、想像するしかない。
しかし、さなえは自分自身が切実な状況に置かれてみて、文島の名もない神社で、息子の希敏と並んで、思わず祈る。
さなえは、祈るとはどういうことか、しみじみ感じたに違いない。みっちゃん姉の祈る姿を思い出しながら。
ところで、物心ついてから養子に貰われた子供というのは、しばしば新しい母親にべったりと纏わりつき、
母親の肩口に登ってお腹のほうに降りてくる、という行動を繰り返すことがあるという。
まるで、「自分は本当はこんなふうに、この母親の子宮から外に降りてきたかったのだ」ということを示すかのように。
この小説でも、主人公さなえは、癒しの貝殻があるという言い伝えのある文島への道を「たしかにこの道を通ったことがある」 (p426下段15行目)と既視感を持って感じている。
さなえは(そして希敏も)、文島行きを通して、より良い再生を迎えることができるのだろうか?
会ではほかに
「方言がこの小説の雰囲気を作っている。母親の胎内に戻るような懐かしいような雰囲気。」
「さなえは、母親に悪態はつくが、希敏に対してはそれほどではなく、希敏を愛し、引き受けていこうという覚悟があるようで立派だ。」
「『引きちぎられたミミズ』という比喩があまりに多用されすぎ。説明しにくい動作を説明するのが面倒なので、 比喩で済ましてしまっているのでは。」
「聖なる文島にリアス式海岸が手を伸ばしているようだ、という比喩はきれいだ。」
などと意見がありました。
今回も充実した議論ができました。
参加者の皆様に感謝申し上げます。
トップページに戻る